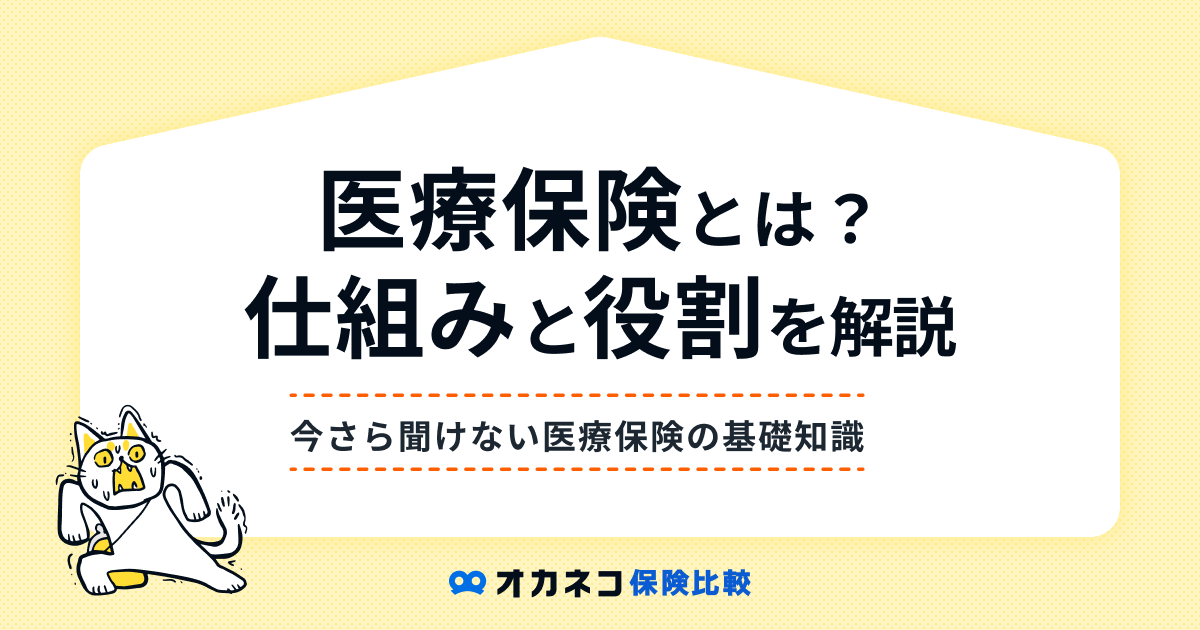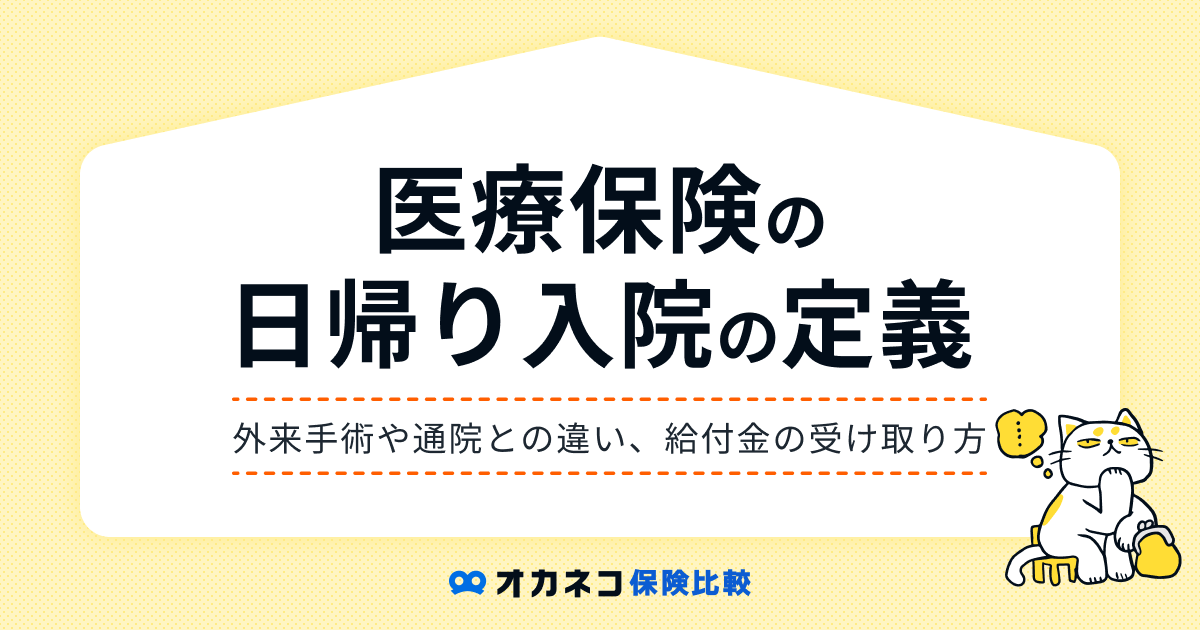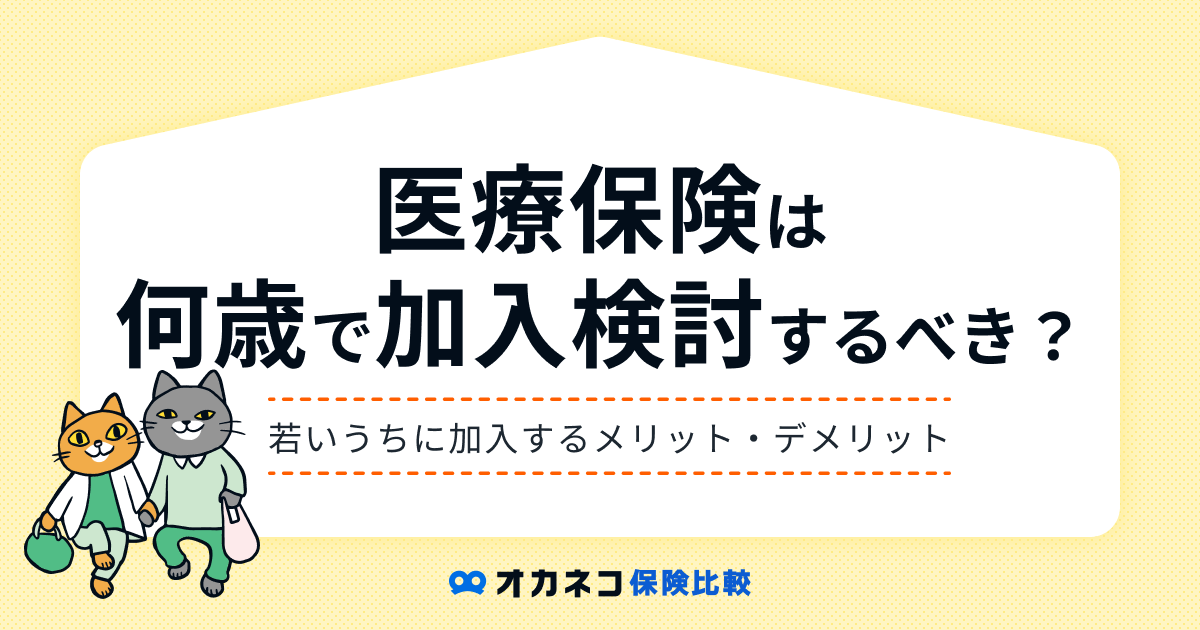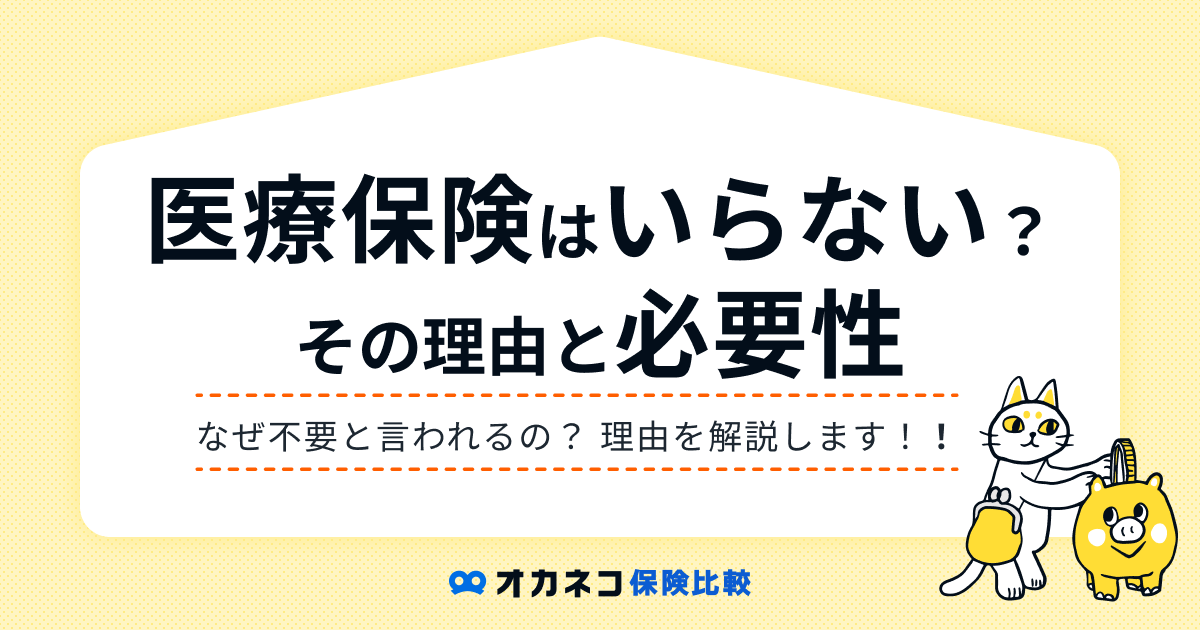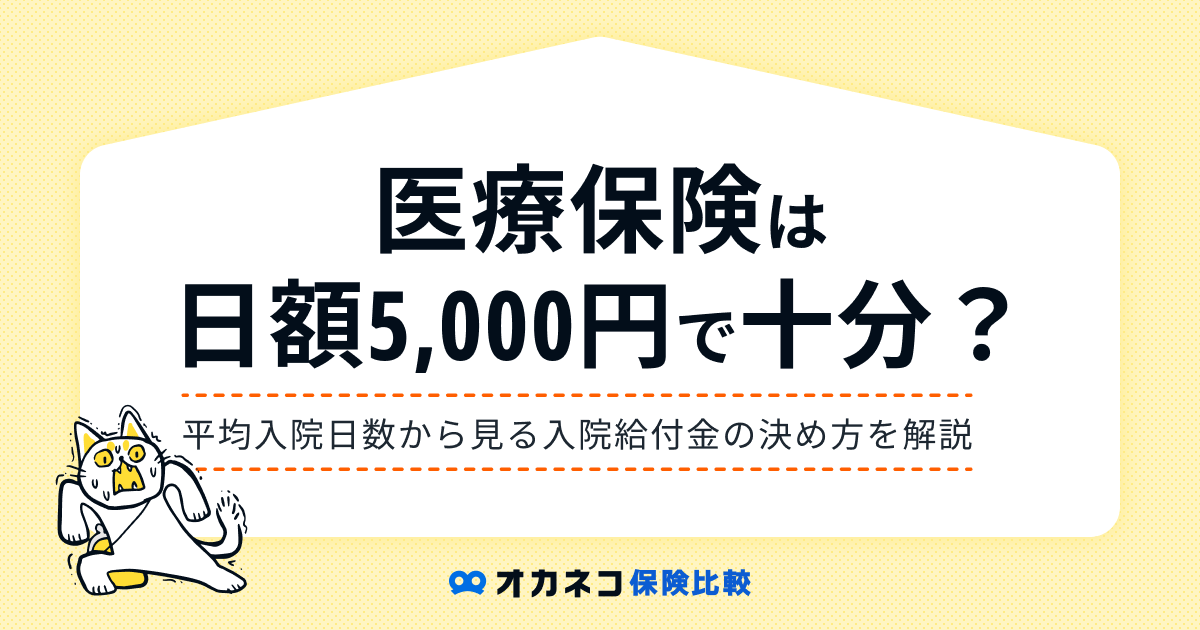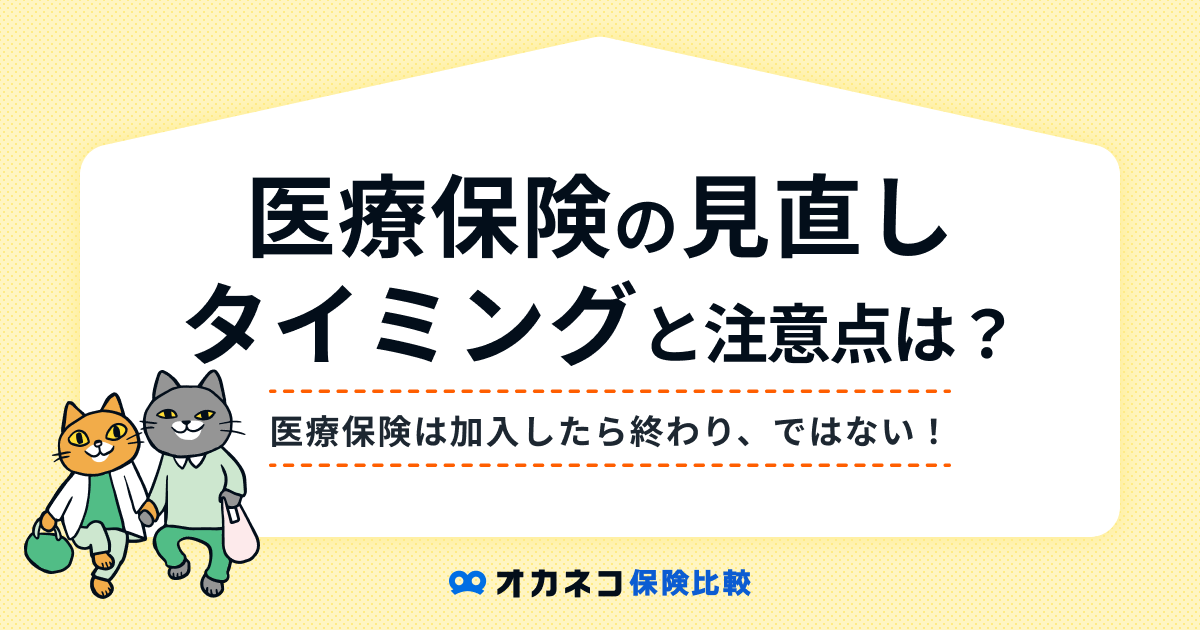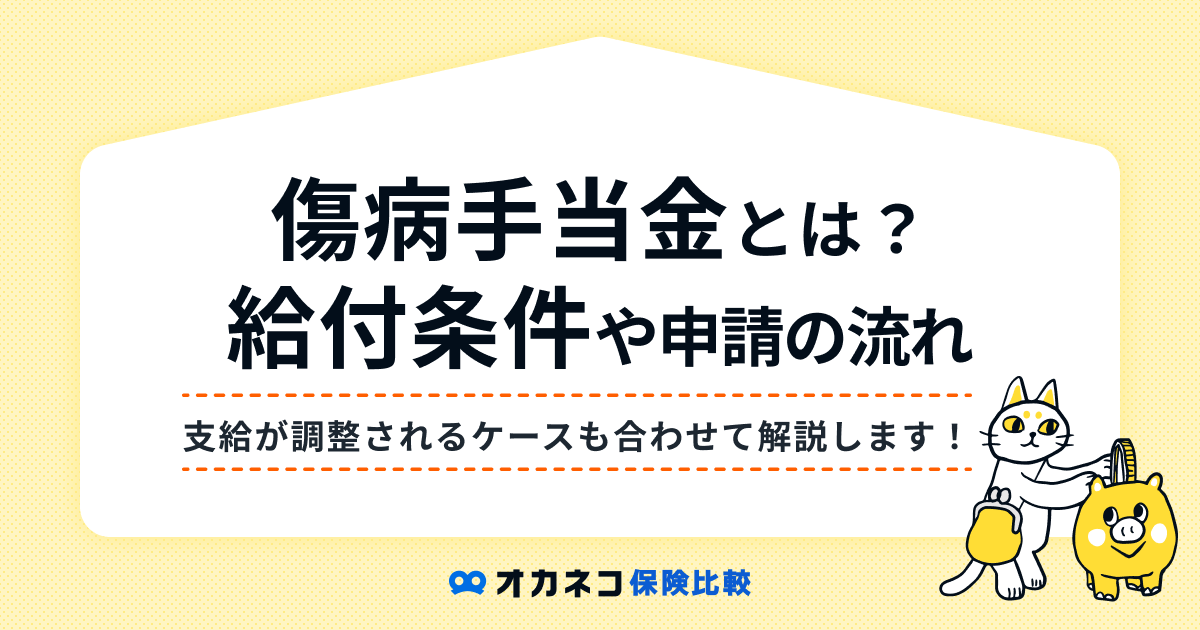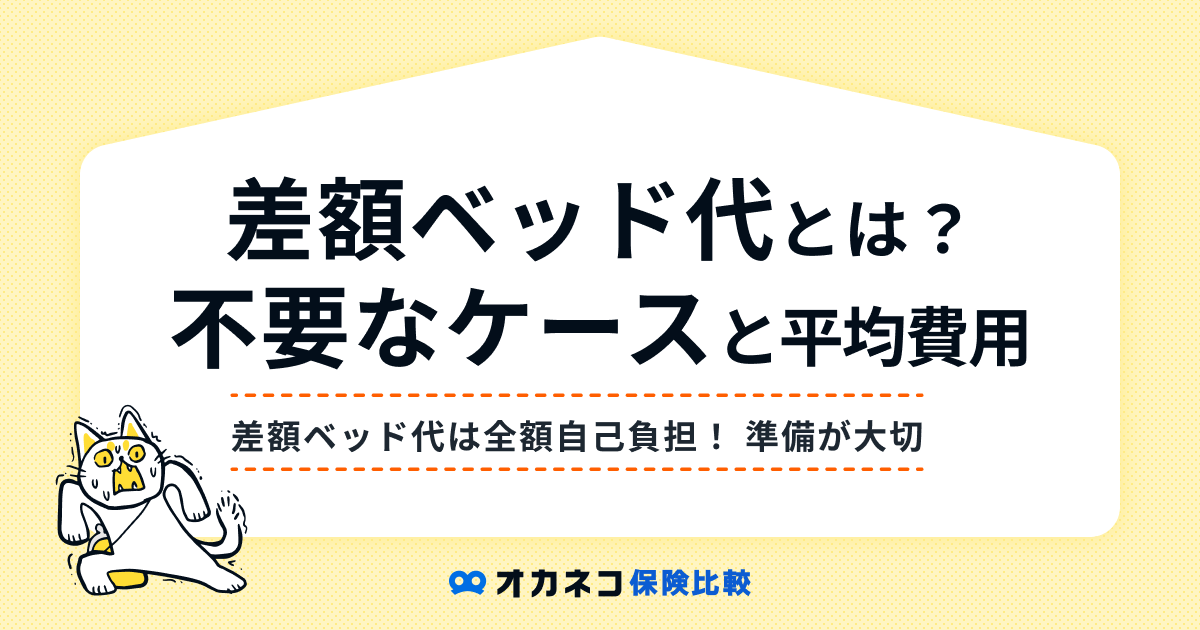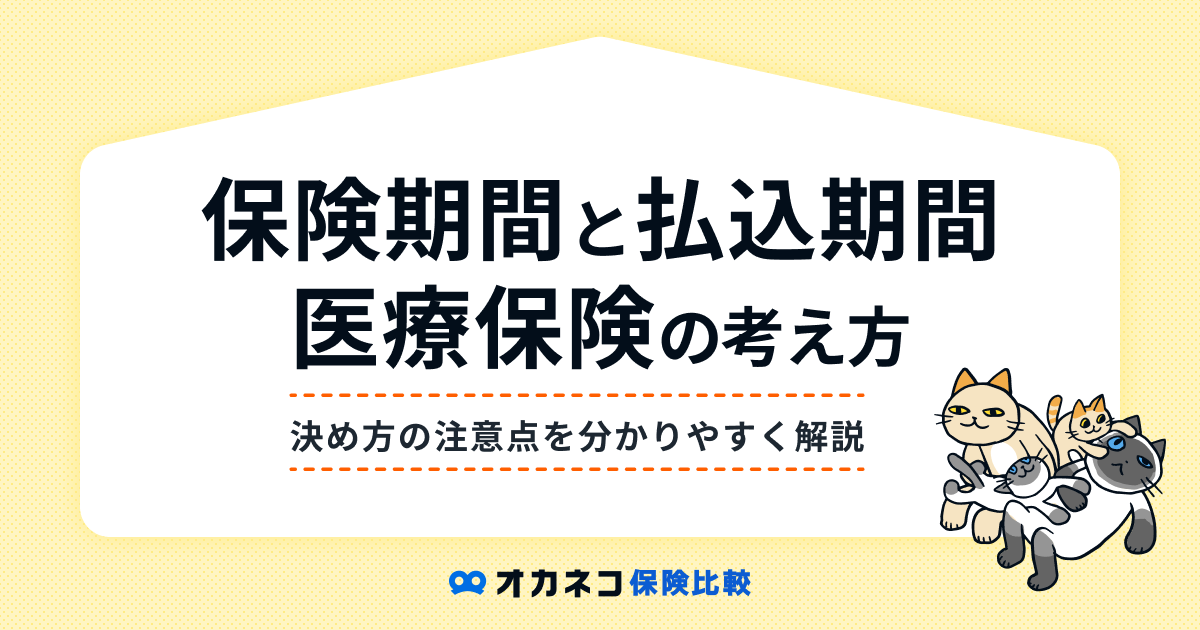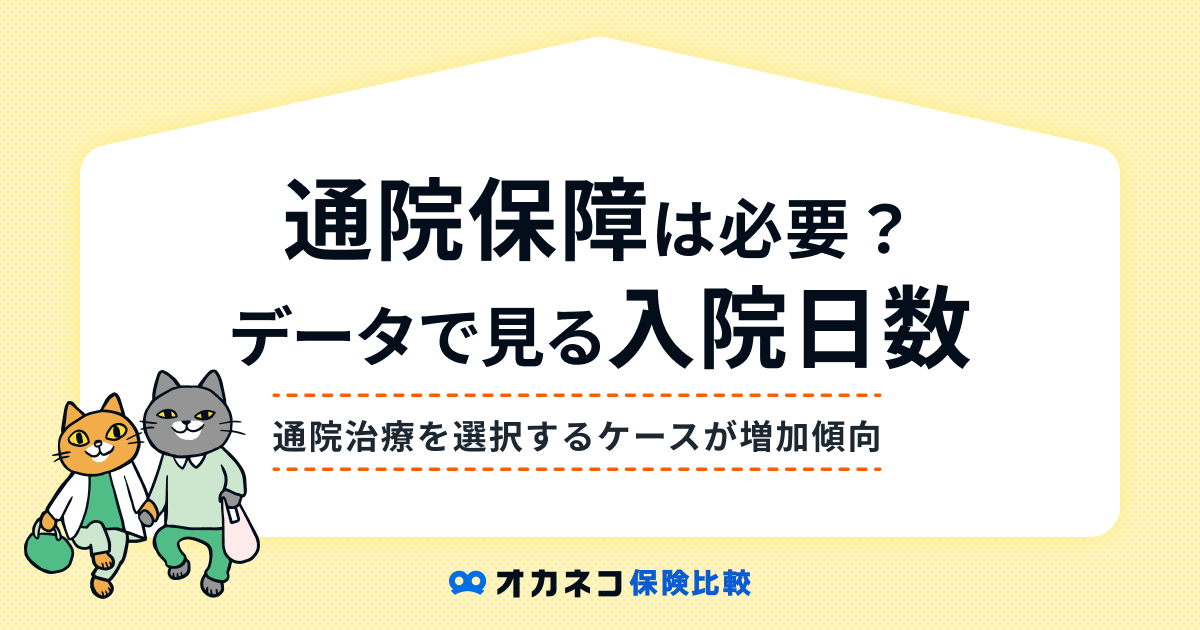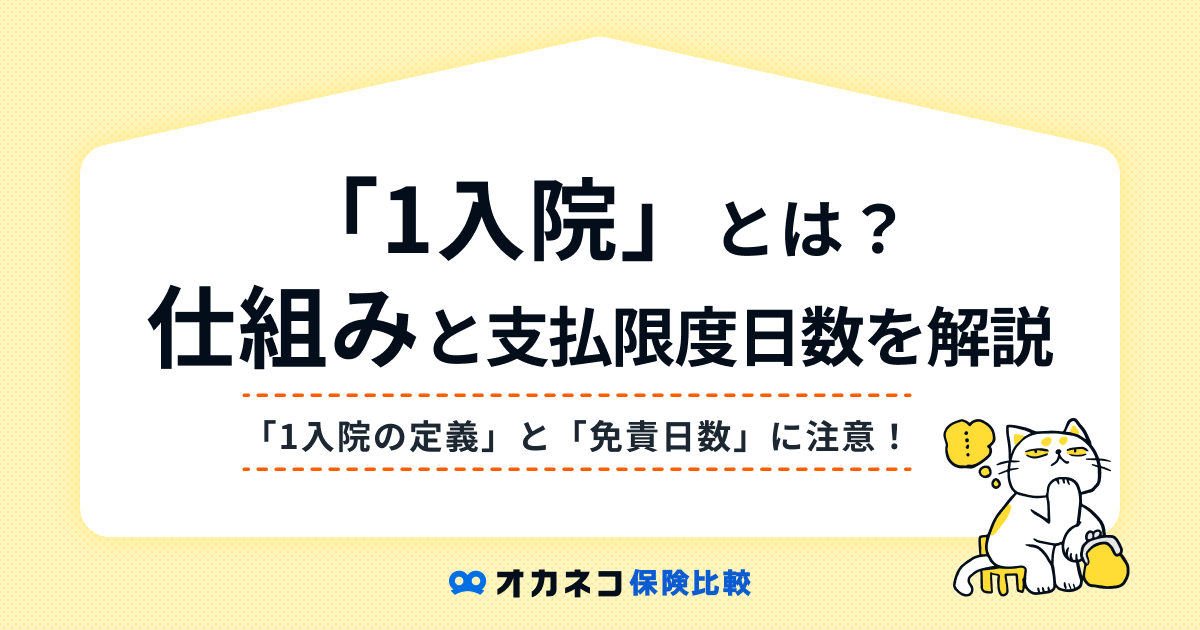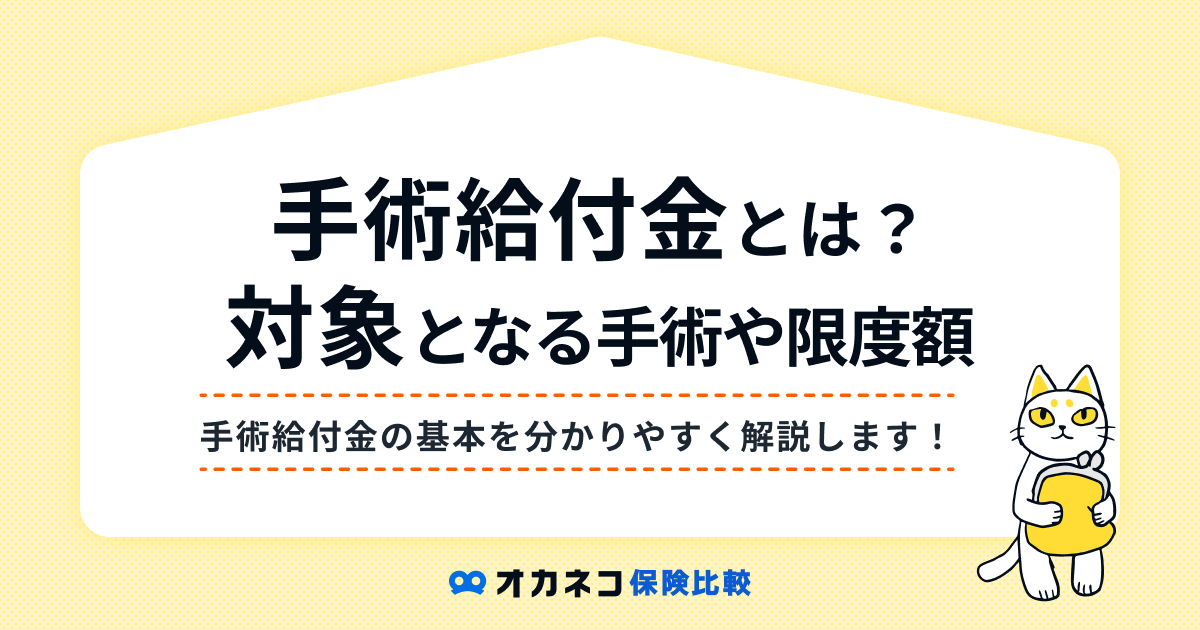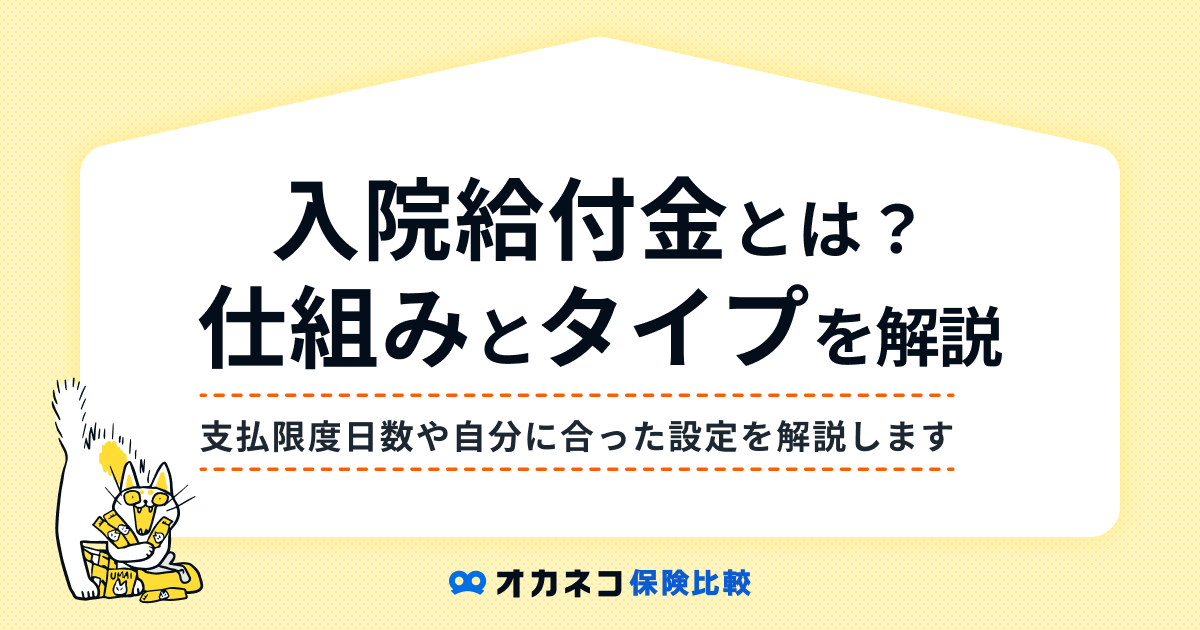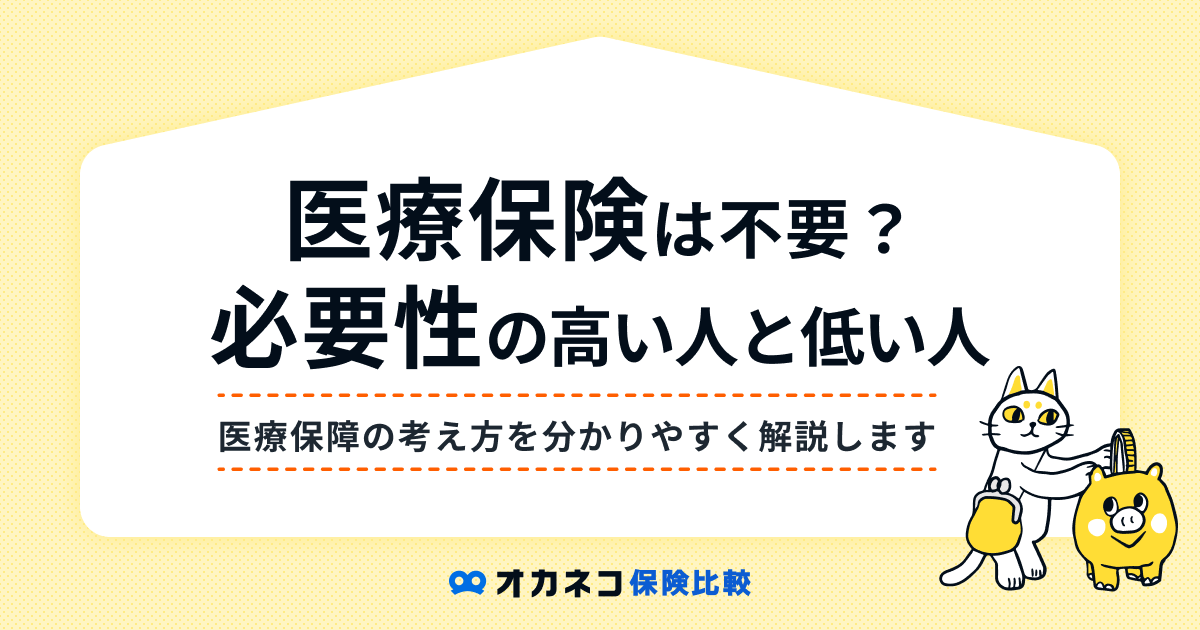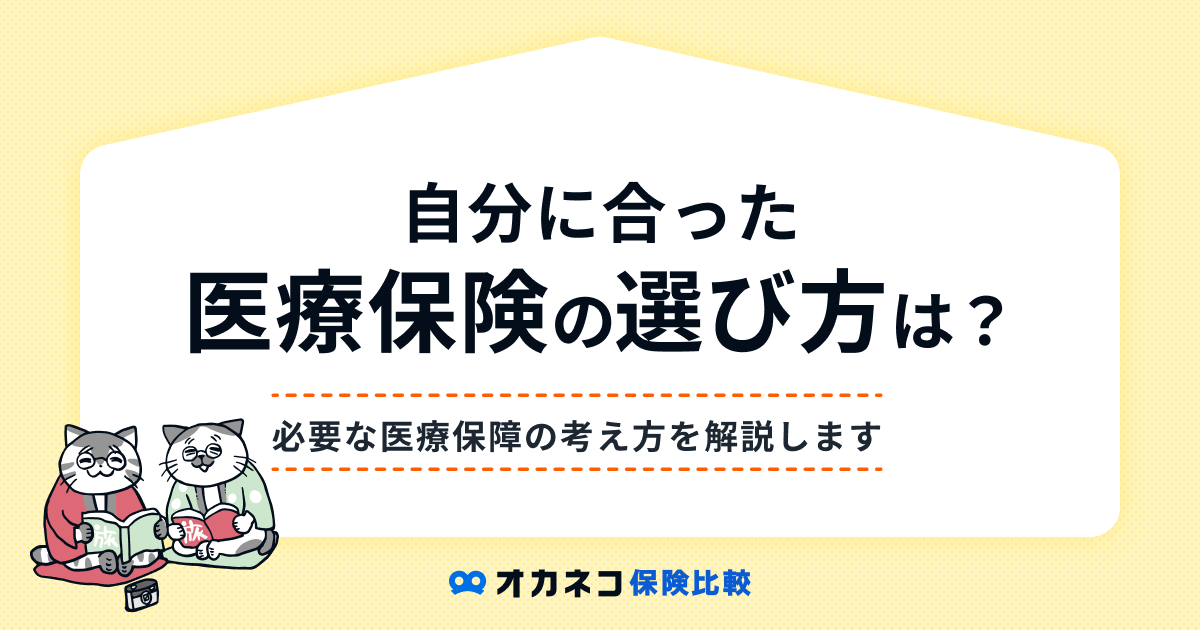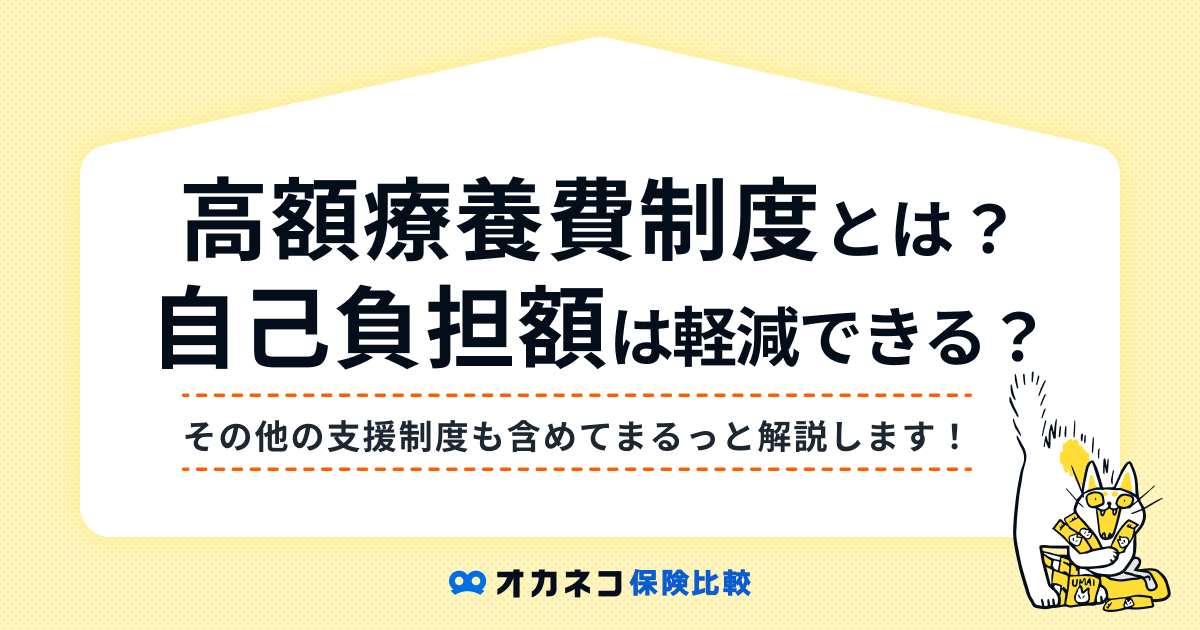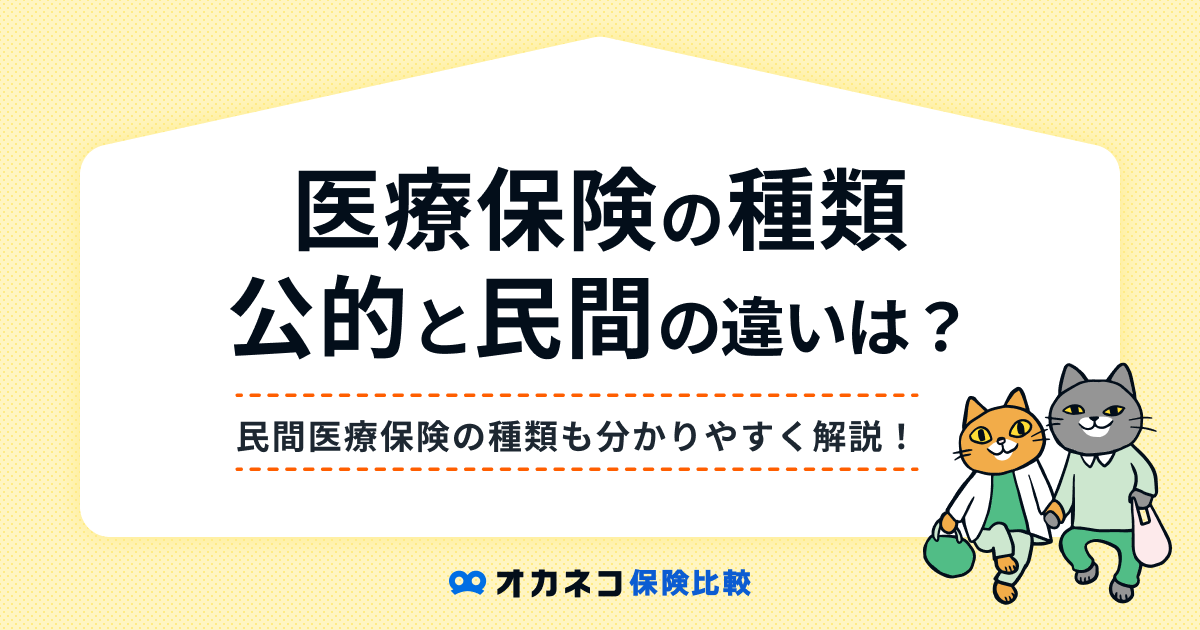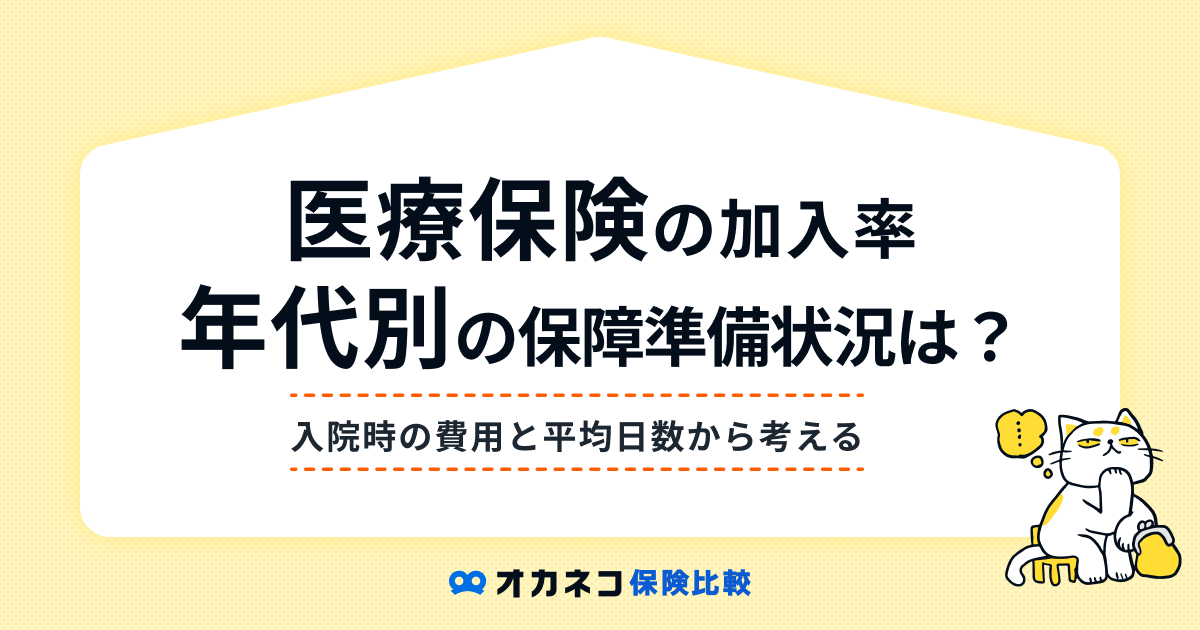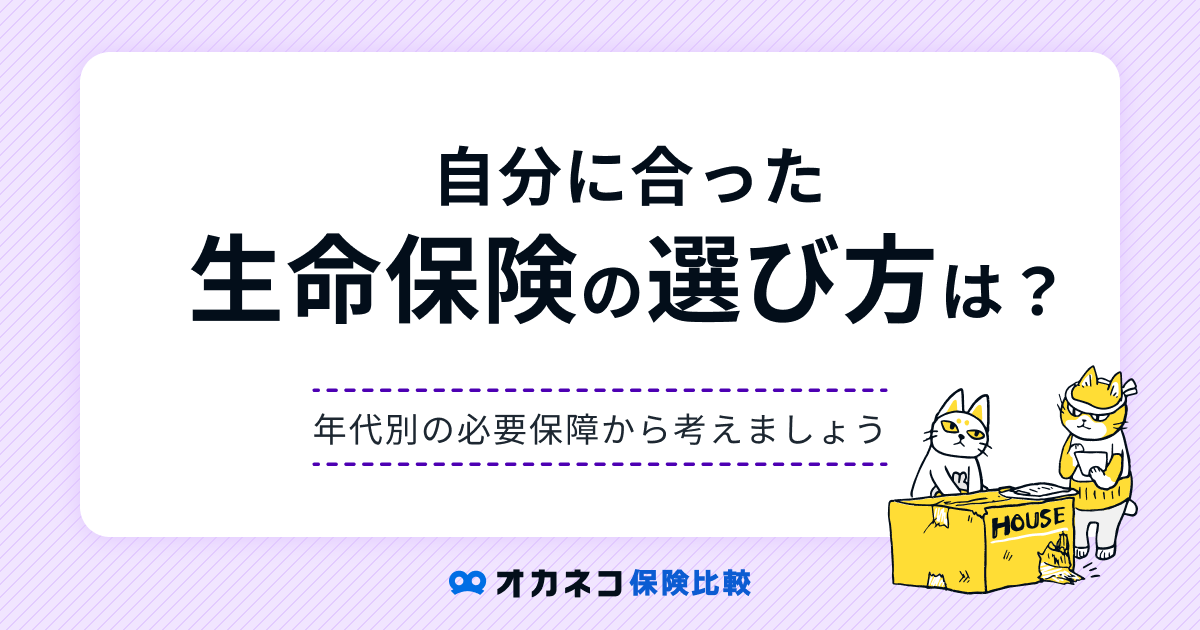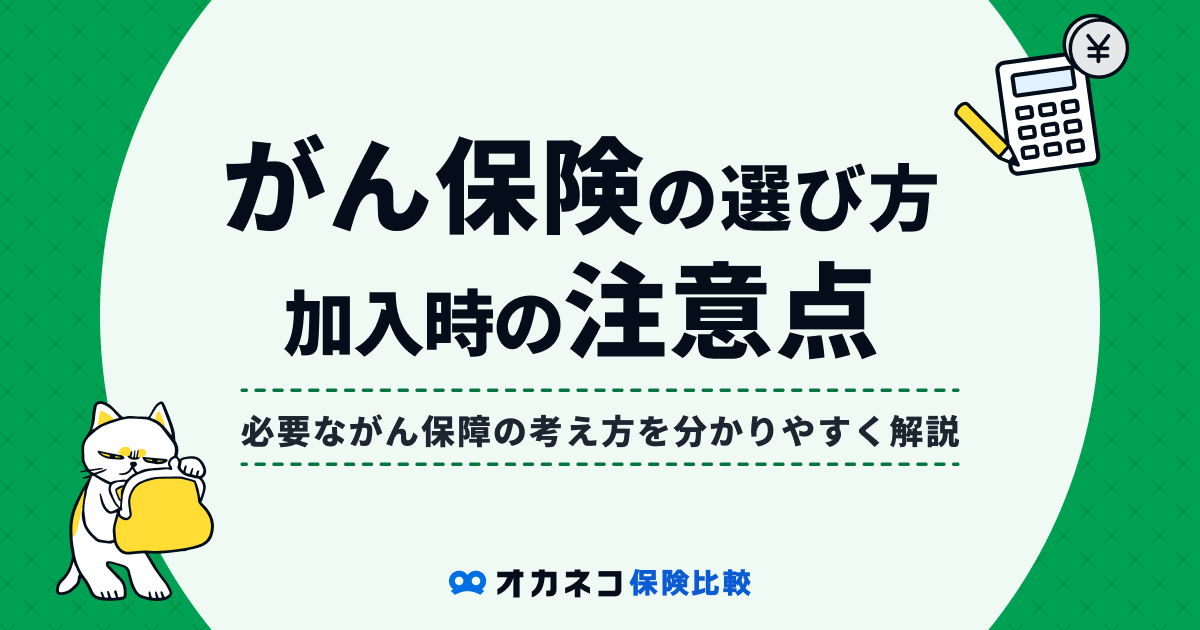監修者

豊田 眞弓
AFP、DCプランナー2級 住宅ローンアドバイザー スカラシップアドバイザー 相続診断士、終活アドバイザー
医療保険とは
日本の医療保険は、国民皆保険制度に基づいて運営される「公的医療保険」と、免許を取得した一般企業が運営する「民間医療保険」の2種類に分けられます。
どちらの医療保険も基本的な仕組みとしては、加入者全員で保険料を出し合い、保障を必要とする方への給付を行う「相互扶助」の精神で成立していることが特徴です。公的医療保険は社会保障のしくみであることから公費も投入されています。
一方、それぞれの医療保険は役割が異なっており、公的医療保険はケガや病気で診療を受ける際の医療費の一部を保障しているのに対し、民間医療保険は商品によって保障内容が異なります。
基本的な考え方としては、公的医療保険で保障されない範囲をカバーするために民間医療保険が活用される位置づけにあります。
この記事に関する保険商品ランキング
調査概要:申込数をもとに算出。オカネコ保険比較調べ、集計期間:2025/12/16〜2026/01/15(申込数が同数の場合は、資料請求数と各社ソルベンシーマージン比率をもとに算出) ※ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。
監修者からのひとこと

豊田 眞弓
AFP、DCプランナー2級 住宅ローンアドバイザー スカラシップアドバイザー 相続診断士、終活アドバイザー
公的医療保険と民間医療保険の違い
ここでは、公的医療保険と民間医療保険それぞれの違いについて確認していきましょう。
| 公的医療保険と民間医療保険の違い | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 公的医療保険 | 民間医療保険 | ||||
| 対象者 | 日本国民※ | 加入者(保険会社が定める要件を満たす人) | ||||
| 加入義務 | あり | なし | ||||
| 加入審査 | なし | あり | ||||
| 保険料 | 前年度の所得を元に計算(医療分・支援金分・介護分の合計)会社員は職場が半分負担 | 年齢、保障内容、加入時の告知事項などに応じて変動 | ||||
| 代表例 | 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など | 医療保険(終身・定期)、がん保険、三大疾病保険など | ||||
日本では国民皆保険制度が採用されており、日本国民は「国民健康保険」や「健康保険」など、何かしらの公的医療保険への加入が義務付けられています。
公的医療保険のおかげで病院を受診する際は医療費の最大3割※を負担するだけで、日本中のどこにいても誰もが高度な医療を受けられることが特徴です。
※6歳未満や70歳以上は1~3割
それ以外にも、出産時に支給される「出産手当金」や「出産育児一時金」、病気やケガの療養のために会社を休んだ場合の「傷病手当金」など、様々な形で保険給付が行われています。
一方の民間医療保険は、各個人が任意で加入することができ、場合によっては全く加入しないという選択肢もあります。
民間医療保険による保障は公的医療保険とは異なり、保険会社や商品ごとに決められた支払事由に該当した場合に「保険金」という形で現金が支給されます。
支給された保険金の使用目的は限定されていないため、入院費用や手術費用への充当はもちろんのこと、長期入院による収入減少時の生活費の補填など、様々な支払いに充てられることが特徴です。
この記事に関する保険商品ランキング
調査概要:申込数をもとに算出。オカネコ保険比較調べ、集計期間:2025/12/16〜2026/01/15(申込数が同数の場合は、資料請求数と各社ソルベンシーマージン比率をもとに算出) ※ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。
主な公的医療保険制度
公的医療保険は「国民皆保険制度」とも呼ばれており、国民は以下の5種類のいずれかに加入することが義務付けられています。
基本的な保障内容は同じですが、それぞれで加入対象が異なるので、次の一覧表で確認しておきましょう。
- 国民全員を公的医療保険で保障
- 医療機関を自由に選べる(フリーアクセス)
- 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するために公費を投入
参照:我が国の医療保険について|厚生労働省
| 主な公的医療保険制度の種類 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 運営元 | 加入対象者 |
| 健康保険 | 健康保険組合 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 会社員及びその扶養家族 |
| 共済保険(共済制度) | 各共済組合 | 公務員及びその扶養家族 |
| 船員保険 | 全国健康保険協会 その他船員保険部など | 船員及びその扶養家族 |
| 国民健康保険 | 各都道府県+市町村国保 国民健康保険組合 | 75歳未満で上記のいずれにも加入していない方 |
| 後期高齢者医療制度 | 後期高齢者医療広域連合 | 75歳以上の方 65〜75歳未満で一定の障害を持つ方 |
参照:保険者及び保険者番号について|全国健康保険協会 船員保険
会社員やその扶養家族は勤務先の「健康保険」に加入することになり、保険料は毎月の給与から差し引かれる形で支払います。
保険料は勤務先との折半で、病気やケガの療養で仕事を休んだ場合の傷病手当金、子どもが生まれたときの出産手当金や出産育児一時金など、手厚い保障を受けられることが特徴です。
基本的な保障内容は船員保険や共済保険も同様で、突然の事故や病気で働けない状態になっても、企業に属している方はある程度の経済リスクが保障されています。
一方、自営業やフリーランスの方、扶養されていない学生など、上記の各公的保険に加入していない方は、もれなく「国民健康保険」に加入します。
国民健康保険の基本的な保障内容は他の公的医療保険と同じですが、その一方で、健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付金はありません。また、扶養という概念がないため、国民健康保険の場合は、家族全員に保険料が発生します(支払いは世帯主がまとめて行います)。
病気やケガで働けなくなると会社員と異なり傷病手当金が出ないため、収入面に大きな不安が残ります。国保加入者やその家族は、後述の民間医療保険やそれまでの貯蓄など、自助努力で万が一の事態に備える必要があります。
公的医療保険の医療費負担の割合
公的医療保険のメインとなる給付内容は「療養の給付」です。
健康保険証を提示することで公的医療保険が適用され、医療費の1〜3割を負担すれば医療機関で必要な医療を受けられます。
医療費の自己負担割合は、年齢や所得に応じて異なるので、次の一覧表でご確認ください。
| 公的医療保険の医療費負担の割合 | |
|---|---|
| 年齢 | 自己負担割合 |
| 6歳未満(未就学の6歳児含む) | 2割負担 |
| 6歳〜70歳未満 | 3割負担 |
| 70〜74歳未満 | 一般:2割負担 現役並みの所得:3割負担 |
| 75歳以上 | 一般:1割負担 一定以上の所得:2割負担 現役並みの所得:3割負担 |
参照:医療費の一部負担(自己負担)割合について|厚生労働省
多くの方は医療費の3割を負担することになり、6歳未満の子どもは2割負担(自治体の医療費助成により一定年齢まで助成されています)、70歳以上は所得状況に応じて1〜3割の自己負担となります。
70~74歳の負担割合は、国保なら課税所得145万円以上で、健康保険なら標準報酬月額28万円以上で「現役並み所得」と判断され、それ以外の方は2割の医療費負担で済みます。75歳以上の後期高齢者は、現役並みは70~74歳と同じですが、課税所得で28万円以上など一定条件に該当する人は「一定以上所得がある人」として2割負担になります。課税所得28万円未満は1割負担です。
全年代を通して、ひと月あたりの自己負担分が自己負担限度額を超過した場合は「高額療養費制度」を利用できます。
高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢や所得に応じて変動するため、詳細については全国健康保険協会公式サイトまたはお住まいの市町村役場の窓口にてご確認ください。
監修者からのひとこと

豊田 眞弓
AFP、DCプランナー2級 住宅ローンアドバイザー スカラシップアドバイザー 相続診断士、終活アドバイザー
民間医療保険の役割
民間医療保険は、生命保険業や損害保険業の免許を取得した一般企業が販売する保険商品です。
公的医療保険とは異なり個人の判断による任意加入で、民間医療保険は治療費の自己負担分を保障するだけでなく、治療にかかる諸費用にも対応できます。
- 自由診療費
- 先進医療費
- 入院中の生活費
- 入院中の食事代
- 差額ベッド代
- 通院治療時または入院時の家族分の交通費
これらの諸費用は、公的医療保険の保障対象外となっているため、基本的には全額を自己負担で賄わなければなりません。
ですが、民間医療保険に加入していれば、支払事由に該当した場合に保険金が支給されるため、高額な医療費が発生した場合でも安心して治療に専念できることが特徴です。
言い換えれば、民間医療保険は公的医療保険で保障されない範囲をカバーすることが目的の保険で、上手に活用すれば、特定疾病(がんや三大疾病など)に対する手厚い保障を得ることもできます。
この記事に関する保険商品ランキング
調査概要:申込数をもとに算出。オカネコ保険比較調べ、集計期間:2025/12/16〜2026/01/15(申込数が同数の場合は、資料請求数と各社ソルベンシーマージン比率をもとに算出) ※ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。
監修者からのひとこと

豊田 眞弓
AFP、DCプランナー2級 住宅ローンアドバイザー スカラシップアドバイザー 相続診断士、終活アドバイザー
医療保険の種類
代表的な民間医療保険は、主に次の4種類が挙げられます。
| 代表的な民間医療保険の種類 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 特徴 | ||
| 定期医療保険 | 一定期間のみ手厚い医療保障がカバーできる | ||
| 終身医療保険 | 一生涯の医療保障をカバーできる | ||
| 女性保険 | 女性特有の疾病(乳がん、子宮頸がん、その他)に対して手厚い保障をカバーする。定期型も終身型もある。 | ||
| 引受基準緩和型医療保険 | 加入時の告知事項が少なく引受基準が緩和された医療保険。持病がある方や既往歴のある方でも加入しやすい。その分保険料は高め。 | ||
民間医療保険には、保険期間が異なる「定期医療保険」と「終身医療保険」の2種類があります。
終身医療保険は加入時の保険料のまま一生涯に渡って保障を受けられる点が魅力的ですが、その代わりに同じ保障内容の定期医療保険に比べ、毎月の保険料負担は割高です。
そのため、子どもの独立や住宅ローンの完済までなど、一定期間に手厚い医療保障を備えたい場合は定期医療保険を活用して、保険料を抑えながら大きな医療保障を準備する方法もあります。ただし、定期医療保険は10年ごとなどに更新をしていくタイプのため、保険料が高くなっていくことや、80歳までなどで保険が終わってしまう点は注意しましょう。
一方、終身医療保険は一生涯の保障で安心です。しかも、途中解約をすると、それまでに払い込んだ保険料に応じた解約返戻金を受け取れる場合があります(商品によります)。
一生涯の保障が欲しい方は、毎月の家計収支を把握して無理のない範囲で終身医療保険を検討するのが向いています。ただし、長い間加入する間に医療の進化と保障内容にずれが生まれる可能性もあり、終身型でもどこかで見直しをする必要があります。
民間医療保険には、これら以外にも女性疾病に特化した「女性保険」、加入時の引受基準が緩和されていることから持病や既往歴のある方も入りやすい「引受基準緩和型医療保険」などもあります。
この記事に関する保険商品ランキング
調査概要:申込数をもとに算出。オカネコ保険比較調べ、集計期間:2025/12/16〜2026/01/15(申込数が同数の場合は、資料請求数と各社ソルベンシーマージン比率をもとに算出) ※ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。
健康増進型保険とは
健康増進型医療保険とは、加入時の健康状態、加入後の健康増進への取り組み姿勢などによって、保険料の割引が受けられるタイプの医療保険です。
- BMI
- 血液検査・血圧
- 尿蛋白
- 喫煙歴
- その他健康診断の結果、運動習慣など
商品によっては医療保険の特約として「健康増進特約」を付帯する形で加入することも可能で、保険会社や商品によって特約分の保険料が無料、またはかかっても数百円程度です。
一部の健康増進型医療保険では、保険料割引の代わりに特別還付金が支給される場合もあるので、日頃から運動習慣がある方や健康状態に自信がある方は、比較する際に検討してみるといいでしょう。
まとめ
日本の医療保険には、大きく分けて「公的医療保険」と「民間医療保険」の2種類があります。
診療機関の受診時に健康保険証を提示することで公的医療保険が適用され、年齢や所得状況に応じて1〜3割の医療費を負担するだけで、日本中のどこでも高度な医療を受けられます。
ただし、公的医療保険では、自由診療費や先進医療費、差額ベッド代、入院中の食事代などは保障されません。
これらの公的医療保険でカバーされない範囲については、民間医療保険の支払事由に該当すれば保険金を受け取れるので、万が一の場合でも経済的リスクを気にせず治療に専念できます。
ただし、民間医療保険の保障内容を手厚くするほど毎月の保険料負担も大きくなるため、公的医療保険の保障を前提に、毎月の家計収支を把握して無理のない範囲で検討するようにしましょう。
この記事に関する保険商品ランキング
調査概要:申込数をもとに算出。オカネコ保険比較調べ、集計期間:2025/12/16〜2026/01/15(申込数が同数の場合は、資料請求数と各社ソルベンシーマージン比率をもとに算出) ※ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。
監修者

豊田 眞弓
AFP、DCプランナー2級 住宅ローンアドバイザー スカラシップアドバイザー 相続診断士、終活アドバイザー